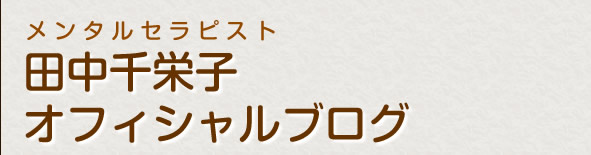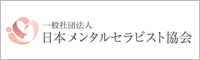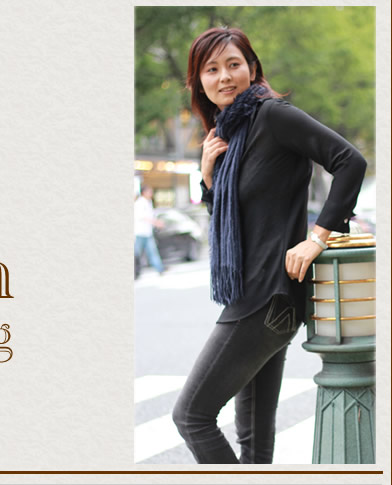
行動パターンを読まれてる
2011年10月25日
洗面所で長い時間、髪を整えていました。
そろそろカットかな?
なんだかまとまらないなぁ?
ん?あれ?傍にいるはずが・・・
愛犬は傍にいません。
いつもは鏡越しに見ているはずなのに・・・
小さなストーカーと呼んでいます。
愛犬はトイレに入ってもドアの前にいます。
パソコンの部屋にいても傍で寝ています。
ソファーに座れば乗ってきてじゃれてくるかくっついて眠ります。
私が昼寝を始めたらハウスで同じように眠ります。
それが・・・いない。
探しました。するとハウスにいます。
どうやら私はこれから出かけると誤解しているようです。
出かける前にはバタバタして着替えたりメイクをして消える
そのパターンに入っていたのでしょう。
出かける準備中は確かに傍にはいません。
行ってきます。と玄関で声をかけてもでてきません。
遠くから仁王立ちでこちらを見ているだけです。
それが抵抗というか意思表示です。
帰ってきた時も喜び半分怒りがあります。
だから甘噛みをしながらじゃれてきます。
言葉を話せないけどしっかり個性があり気持ちがある
そんな犬です。
ただ誤解させてしまった事に笑えますが・・・
私の行動パターンを客観的に観察されている事に恥ずかしくなりました。
犬に読まれているのです。
動物は何を感じ人を判断しているのだろう?
私達は会話する言葉や態度など人間関係で見つめる部分が沢山あるけど
言葉を発して伝えられない動物はそれでも人を見極めている。
沢山の要素を持っているのに人間は見極めたり
把握したり相手の行動パターンを忘れて
時にマナーや道徳心をはずしてしまう。
そしてこの行動パターンを読まれていることに恥ずかしさを覚えました。
それだけ見つめ観察されているひとりの人間として…
出かけないその日は、愛犬サービスディにしました。
いつもより遊び、いつもより散歩を増やしました。
きっと、何で散歩行けたのだろう?
そうは思わないか。。。
ただ「わ〜〜〜い!」くらいだろうな。
人間は社会的動物である
2011年10月22日
精神疾患と社会脳
神経画像研究の知見から
の勉強会へ行ってきました。
京都大学医学研究科
村井教授のお話です。
客観的に
製薬会社と京大精神科の方々
そしてこれから活躍される
学生と興味のある人【私の様な】に
囲まれている空気の中で
1時間半の研究結果と
教授の考えを聞いてきました。
精神科の病気とは
1心の病気
2脳の病気と考える2派に分かれる。
というくだりから始まります。
教授は3「社会行動に関する病気」と捉え
研究していると言う話です。
脳内画像を中心に捉えています。
アリストテレスの言葉
「人間は社会的動物である」との話も理解できました。
しかし私の考えはちょっぴり違います。
その3つをひとつとして見つめてアドバイスをしていたり
この3つの視点から見つめて判断しています。
心の病気には
必ず何か現実で原因があると思っています。
それによって脳にも問題が起きてきます。
そして脳の病気に繋がります。
ストレスも長期にわたれば脳にも影響があると思っています。
長期お薬も同様に捉えています。
その必ずある原因には広大な見えない糸を掴み取るようなものだけれども
きっかけは必ずあると思っています。
原因を探る上で大切な事は
原因を見つけてそのせいにするものではなく
原因は次ぎに起こらないための
予防の為に知ると言う認識として必要と私は考えます。
そして忘れてはならないのは
人間は社会動物であると言うアリストテレスの言葉です。
ここも忘れてはならない部分で
私は癖などの問題でここを見つめています。
人間は動物的な本能や癖と習性などがあり
目指すものが無ければやる気が無くなり
いつもあるものを失うと混乱し心は揺らぐ
統合失調症や欝の方の脳内画像は明らかに
ある部分が小さくなっていたりします。
そこで小さいからおしまいでも、
欝だからおしまいでもありません。
時には病名を診断されて一瞬ほっとする事もありますが
それは一瞬です。
その後はその言葉と共存してしまいます。
私はそれ自体、動物的な部分ではないかとも考えます。
先生とつく名前の方の言葉を
信じ込む部分も強いものに従う部分ではないかとも
思うことがあります。
どんな病気であろうとも
治る力は誰にでも備わっていると信じてお話を聞きます。
私達は動物的な部分もありますが
人間と言う生き物として特別なものも備わっていると考えるからです。
自由意志と自己治癒力と変化です。
変化に対応できる種族であり
前に進んだり進化を恐れない種族として見つめています。
個人の意思に全てが・・・
人生があると私は思って心と人と向き合っています。
もしも手が無ければ足でお箸を持てばいい
目が無ければ耳で情景を聞いてイメージすればいい
欝になったら
欝抑制になる現実的なことをすればいい
統合失調症での人間関係の問題は
癖やパターン、理由を聞いて納得して
行動も対応も癖をつければいい。
私達はどんな人間になろうとも
それに負けない
それに適応して改善すべくだけの種族であると
この点に関しても客観的に言えます。
白から黒にはならないけど
黒を知る事はできるはずです。
人の気持ちが理解しにくい人もいれば
人の気持ちがわかりすぎて辛くなる人もいます。
自分の心が苦しくなる時もあれば
何も感じなくなることもある。
理解したいと思えば少し感じられる。
苦しい時は少し楽になる事だって出来る。
何も感じなくなっても少しずつ感じられるようにはできる。
自由意志の決定で・・・
その変化には癖を改めなくてはいけない事もある
それがこのお話での社会的動物だからです。
今回は難しいお話になってしまいましたが
人の意見を耳にして自分はどうあるべきで
どうしているのか?
いつも自己確認をさせてもらっています。
心は様々な分野で研究されていますが
どれも正しいと考えているからこそ
ついつい
報告もかねて
記録として気持ちを書いてみました。
次回は人間の感覚である
嗅覚(フェロモン)についての研究報告です。
そのお話も楽しみにしている部分です。
心に伝わる言葉っていい
2011年10月19日
文章でも言葉でも心に響く言葉は
なんだか心地よい。
素直になれるような気がする。
感情に素直になれたり
こころのまま受け入れられる。
でも言葉にもいろいろある。
「ありがとう」と言う言葉でも
心に響かない事もある。
時にはイラッと来る「ありがとう」もある。
涙が出るほど嬉しい「ありがとう」もある。
それは「ごめんなさい」にも言える。
きっと心は
言葉や態度、
そして表情を通して何かを感じ取っている。
感受性の高い人はもちろん
誰もが何かを感じている。
言葉と笑顔とで気持ちを込めて
何かを伝えられたら・・・
きっと誰もがわかってくれると信じてる。
それくらいの表現をしなければ
人はよりよく感じられないかもしれない。
本当にわかってほしいなら・・・。
それは笑顔だけではなく
怒りも不安も
同時に伝えなくてはいけない時だってある。
喜怒哀楽はどれもが大切だと私は思う。
ただ、バランスが崩れてしまえば
表現である言葉や感情をぶつけすぎても良くない。
子供の時は自由でいい
でも子供と大人の違いは
その出しすぎない表現にあるような気がする。
暴言にならない言葉の選び方なのかもしれない。
素敵な美しい言葉ばかりではなく
本当に心に伝わる言葉とは
どの感情も表現できる事なのかもしれない。
真実の伝わる言葉とは
美しさも心の不安も言葉の中でバランスよく
気持ちをより伝えられる事なのかもしれません。
- 田中千栄子 経歴を見る
- 一般社団法人日本メンタルセラピスト協会 専務理事
日本メンタルセラピスト協会HP - http://www.jmental.com/
- 最近心の活動に熱い関心を持たれている方がいらして嬉しく思います。
-
協会ではテキストも中身を見て、立ち読みをして購入くださいとしております。心を扱う人になるには押しつけの心は良くないからなんです。そんな愚痴ではありませんが、この協会の中心にある趣旨(核)がこちらの無料電子書籍です。ハーフの読み物ですが興味のある方はこちらをダウンロードしてみてご覧ください。
この無料電子書籍の後に協会が出来ました。素敵な人の協力があって検定協会があります。
書籍内のホームセラピスト倶楽部って協会の事なんですよ。進化してしまっていますが趣旨のみご理解いただけるとありがたいです。 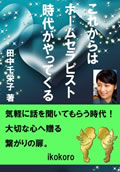
- このブログの読者になる
- RSSリーダーのご利用で、このブログの更新情報をいち早く入手できます。